皆さん、こんにちは! キツネ博士じゃ。 わしらの体を守る免疫システムが、時として自身の体を攻撃してしまう病気がある。その一つが「潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis: UC)」じゃ。この病気は、大腸の粘膜に慢性的な炎症を引き起こし、多くの患者さんを生涯にわたって苦しめておる 。
近年、「TNF阻害剤(TNFi)」という優れた治療薬が登場し、多くの患者さんを救っておる 。しかし、残念ながらこの薬が初めから効かない人や、途中で効かなくなってしまう人が少なからずおるんじゃ 。さらに不思議なことに、この病気には男女で症状の出方や薬の効きに違いがあることも報告されておる 。
なぜ薬が効く人と効かない人がいるのか?なぜ男女で違いが生まれるのか? この複雑な病態を解き明かすには、「どんな細胞が、組織のどこで、何をしていたか」を正確に知る必要があった。
本日紹介する研究(Mayer et al., Science Advances, 2023)は、「CODEX」という最新のイメージング技術を駆使し、UC患者さんの腸の組織をかつてない解像度でマッピングした、まさに「病巣の詳細な地図帳(アトラス)」を作成した画期的なものなんじゃ 。
52色のインクで描く「細胞の社会地図」
これまでの研究、例えばシングルセルRNA-seq(scRNA-seq)では、組織をバラバラにしてしまうため、「どんな細胞がいるか」はわかっても、それらが「組織のどこにいたか」という最も重要な空間情報が失われてしまっていた 。
そこで研究チームは、CODEX(CO-Detection by indEXing)という技術を用いた。これは、52種類ものタンパク質(バイオマーカー)を、一つの組織切片上で同時に、かつ位置情報を保ったまま染色・撮影できる技術じゃ 。29人のUC患者と5人の健常者から得た組織を使い、合計170万個以上もの細胞一つひとつに、52色の「個性」と「住所」を記録した、広大で高精細なデータアトラスを構築したんじゃ 。
発見1:細胞は「ご近所」で機能する
この詳細な地図を解析した結果、細胞はバラバラに存在するのではなく、特定の細胞同士が集まって機能的なグループを形成していることがわかった。研究チームはこれを「細胞近傍(Cellular Neighborhoods: CNs)」と名付けた 。
まるでわしらの社会と同じじゃな。「住宅街(上皮細胞のCN)」もあれば、「ビジネス街(間質細胞のCN)」、「防衛基地(B細胞濾胞のCN)」、「繁華街(炎症性血管のCN)」といったように、10種類の異なる「ご近所」が特定されたんじゃ 。
さらに重要な発見は、個々の細胞の機能状態(個性)は、その細胞がどの「ご近所」に住んでいるかに強く影響されることじゃった 。例えば、同じT細胞でも、B細胞濾胞(CN-9)にいるT細胞はPD-1を強く発現しておるが、別の免疫エリア(CN-4)にいるT細胞はそうでもない、といった具合じゃ 。
発見2:TNFi治療に抵抗する「抵抗勢力(ニッチ)」の特定
この「ご近所」の概念は、治療抵抗性の謎を解く鍵となった。研究チームは、TNFi治療を受けている患者と受けていない患者の組織を、同じ病気の重症度(Mayo score 2)で比較した。
その結果、驚くべき違いが見えてきた。
- TNFiが効く場所(獲得免疫): T細胞やB細胞が集まる「リンパ球凝集塊(CN-2)」や「B細胞濾胞(CN-9)」といった獲得免疫のご近所は、TNFi治療によって著しく減少し、健康な状態に近づいておった 。
- TNFiが効かない場所(自然免疫): ところが、「顆粒球のご近所(CN-3)」のような自然免疫の細胞が集まるエリアは、TNFi治療の影響をほとんど受けずに、炎症組織に居座り続けていたんじゃ 。
これは、TNFi治療が獲得免疫系の炎症は鎮圧できるものの、自然免疫系が中心となった炎症の「ニッチ(聖域)」は攻撃できず、これが薬の効かない「抵抗勢力」として残存している可能性を強く示唆しておる 。
発見3:治療反応における「性差」のヒント
さらに、このアトラスは「性差」の謎にも光を当てた。この研究コホートでは、これまでの報告通り 、女性患者の方が男性患者よりもTNFi治療に反応する割合が高い傾向が見られたんじゃ(P<0.055) 。
地図を詳しく調べてみると、その理由の一端が見えてきた。女性患者の腸では、男性患者に比べて、T細胞の割合が有意に高かったんじゃ 。そして、このT細胞が多く集まる「リンパ球凝集塊(CN-2)」こそ、先に述べたようにTNFi治療によって劇的に減少する、つまり薬が効きやすい「ご近所」じゃった 。
つまり、女性はもともと、TNFi治療がターゲットとする「獲得免疫」のご近所が活発なタイプの炎症を起こしやすく、その結果として薬が効きやすいのかもしれん。逆に言えば、男性は薬が効きにくい「自然免疫」のご近所が主体となるタイプの炎症が多い可能性も考えられる。もちろん、これは今回のコホートでの発見であり、さらなる検証が必要じゃが、性差医療の重要な手がかりとなるじゃろう。
結論:未来の「個別化医療」への地図
本研究は、CODEXという羅針盤を用いて、UCという複雑な病態の広大な海図を描き出してくれた。この地図は、なぜTNFi治療が効かない患者さんがいるのか(自然免疫ニッチの残存)、そしてなぜ治療効果に性差が見られるのか(T細胞優位か否か)について、強力な生物学的根拠を示してくれた。
また、研究チームはAI(CNN)による画像診断も試みたが、患者数が少ない段階では予測が不安定になることも正直に報告しておる 。これは、AIを医療に応用する上での重要な教訓じゃな。
このアトラスは公開されており(Explorer) 、世界中の研究者がこの地図を基に新たな仮説を立てることができる。今後は、このTNFi抵抗性の「ニッチ」をいかに攻略するかが、UC治療の新たな鍵となるじゃろう。
【今回ご紹介した研究】
- 論文タイトル: A tissue atlas of ulcerative colitis revealing evidence of sex-dependent differences in disease-driving inflammatory cell types and resistance to TNF inhibitor therapy
- 著者: Mayer, A. T., et al.
- 発表年: 2023
- 掲載誌: Science Advances, 9, eadd1166
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.add1166

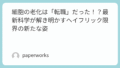
コメント