前回は、クローン病においてYAPシグナルが過剰に活性化し、線維芽細胞が暴走することで腸が硬くなる「線維化」の一因となる、という話をしたのを覚えておるかな。YAPシグナルが、病気の文脈では厄介な働きをすることがわかったわけじゃ。
では、病気ではない正常な状態、つまりわしらの体が健康に保たれている時、このYAPシグナルは一体どんな賢い役割を果たしておるんじゃろうか?
本日紹介する論文(Zhou et al., PNAS, 2022)は、まさにその疑問に答える、素晴らしい基礎研究じゃ。YAPシグナルが、単なる細胞増殖のアクセルではなく、異なる細胞間のコミュニケーションを司る「組織の司令塔」として機能する様子を見ていこう。
細胞社会の多様なルール:「スペース派」と「増殖因子派」
わしらの体は、多種多様な細胞が集まってできた「細胞の社会」じゃ 。この社会がうまく機能するためには、それぞれの細胞が適切な数だけ存在することが不可欠じゃ 。しかし、異なる種類の細胞が、どのようにしてお互いの数を調節しているのか、そのルールは謎に包まれておった 。
この研究では、組織に普遍的に存在する2種類の細胞、「線維芽細胞」と「マクロファージ」に着目した 。そして、これらの細胞が全く異なるルールで自身の数(増殖率)を制御していることを見出したんじゃ。
- 線維芽細胞: 組織の骨格を作るこの細胞は、「空間の利用可能性(スペース)」に非常に敏感じゃった。つまり、周りが混み合ってくると増殖を停止する「スペース派」じゃったんじゃ 。
- マクロファージ: 免疫を担うこの細胞は、自身の増殖に必要な「増殖因子(エサ)」の量に敏感に反応する「増殖因子派」じゃった 。
実験的にも、線維芽細胞の増殖率は細胞密度に強く依存し、マクロファージの増殖率は増殖因子CSF-1の濃度に強く依存することが示された 。まるで、土地の広さを気にする農耕民族と、食料の量を気にする狩猟民族のようじゃな。(逆に、線維芽細胞の増殖率は増殖因子にはあまり依存せず、マクロファージの増殖率は、細胞密度に依存しなかった)
では、全く異なるルールで生きるこれらの細胞たちは、どうやって組織内で調和を保っておるんじゃろうか?
YAPシグナルの真の役割:空間情報を読み取り、細胞間コミュニケーションの指令を出す
ここで再び、YAPシグナルの登場じゃ。研究チームは、
線維芽細胞が「スペース」という物理的な情報を感知するセンサーこそが、Hippo-YAPシグナル経路であることを見出した 。
具体的には、こうじゃ。 細胞密度が低い(=スペースが空いている)と、線維芽細胞はYAP1タンパク質を核の中へ移行させて活性化させる 。逆に、細胞密度が高い(=混み合っている)と、YAP1は核から締め出され、不活性化されるんじゃ 。
前回のクローン病の話では、このYAP1の活性化が線維芽細胞自身の増殖を促し、線維化につながると解説した。しかし、今回の研究は、YAP1の役割がそれだけではないことを明らかにした。活性化したYAP1は、自分自身のためだけでなく、全く別の細胞種であるマクロファージの運命を左右する「指令」を出していたんじゃ!
指令の正体「Csf1」:YAPが司るマクロファージの増殖因子
YAP1が出すその指令の正体は、マクロファージにとっての特異的な増殖因子であるCsf1(コロニー刺激因子1)じゃった 。
驚くべきことに、活性化したYAP1は、Csf1遺伝子の近くにある「エンハンサー」と呼ばれる、遺伝子のスイッチを遠隔操作する領域に直接結合することが、ChIP-seqという技術で突き止められた 。つまり、線維芽細胞は、以下の連携プレーを行っておったのじゃ。
【スペース感知から他者コントロールへの流れ】
- 感知: 線維芽細胞が「スペースが空いている!」と物理的に感知する。
- 伝達: 細胞内のアクチン線維(細胞骨格)が緊張し、その力が核に伝わることでYAP1が活性化(核内移行)する 。
- 指令: 活性化したYAP1が、
Csf1遺伝子のスイッチをオンにする 。 - 実行: 線維芽細胞から放出された
Csf1を受け取ったマクロファージが増殖する 。
この一連の流れは、YAP1を人工的に活性化させた線維芽細胞(YAP1CA)とマクロファージを一緒に培養する実験でも見事に証明された。YAP1CA線維芽細胞と培養すると、マクロファージの数とその比率が著しく増加したんじゃ 。
結論:YAPシグナルは組織の恒常性を司る司令塔
この研究が明らかにしたのは、
組織を構成する異なる細胞集団の数は、それぞれが独立に決めているのではなく、一方の細胞(線維芽細胞)が微小環境(空間)をセンシングし、その情報を基に他方の細胞(マクロファージ)の数を制御するという、極めて合理的で精緻なコミュニケーションシステムが存在するということじゃ 。
この仕組みは、体の恒常性を維持する上で非常に重要じゃ。例えば、組織が損傷して細胞が失われ「スペース」が空いた時、線維芽細胞は即座にそれをYAPで感知し、修復の専門家であるマクロファージを呼び集めるための
Csf1を放出する。これにより、迅速かつ適切な組織修復が可能になるんじゃな 。
前回解説したクローン病の線維化は、この賢いシステムが、慢性的な炎症という異常事態によって破綻し、YAPシグナルが暴走してしまった結果と捉えることもできるじゃろう。
YAPシグナルは、単なる細胞増殖のON/OFFスイッチではない。周囲の環境を読み取り、異なる細胞種の運命までをも司る「組織の司令塔」。生命が持つ、かくも美しき調和の仕組みに、わしは改めて感動じゃの。
今回ご紹介した研究】
- 論文タイトル: Creeping fat-derived mechanosensitive fibroblasts drive intestinal fibrosis in Crohn’s disease strictures
- 著者: Bauer-Rowe, K. E., et al.
- 発表年: 2025
- 掲載誌: Cell, 188, 1-18
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.08.029

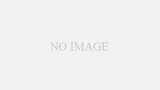
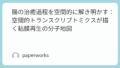
コメント